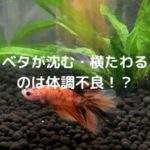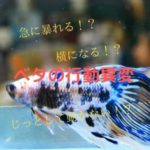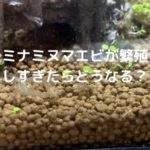ベタが罹りやすい病気は?
ベタの腹水病とはどんな病気?
腹水病の原因と治療方法とは?
ベタの水カビ病とはどんな病気?
水カビ病の原因と治療方法とは?
どちらの病気も薬で完治する?
こんなベタが罹りやすい病気についてご紹介いたします。
目次
ベタの病気についてはこちらのまとめ記事をご覧ください。
ベタが罹りやすい病気とは?
飼育しているベタにはいつまでも元気で長生きしてもらいたいものです。
ですが、生き物を飼っている以上、病気の発生リスクは常につきまといます。
ベタがかかりやすい病気にはどのようなものがあるのでしょうか。
ベタが発症しやすい病気には次のようなものがあります。
- 水カビ病
- 腹水病
- 尾ぐされ病、口ぐされ病(カラムナリス菌が原因)
- 白点病
- コショウ病
- 松かさ病、赤斑病(エロモナス菌が原因)
- ストレスによるヒレの欠損
これらの病気にベタは罹りやすいです。
今回はこの中の「腹水病」と「水カビ病」について、詳しくご説明いたします。
その他の病状については過去の記事をご覧ください。
ベタの腹水病
ベタが罹りやすい病気の1つに「腹水病」というものがあります。
腹水病とは、魚のお腹の中に水が溜まってしまう病気です。
腹水病に罹ると、次のような症状が現れます。
- 食欲が無くなる
- あまり泳がなくなる
- お腹がパンパンに膨らむ
- 糞の回数が減る
- 糞が白くなる
これらの症状が複数見られたら、腹水病に罹っている可能性が高いので、発見次第、すぐに治療を開始しましょう。
腹水病の原因と治療方法
腹水病が発症する原因は、ハッキリと解明されてはいませんが、次のような原因があると言われています。
- エロモナス菌への感染
- 消化器系の内臓疾患
- ストレス
エロモナス菌は淡水域ならどこにでも生息している細菌です。
エロモナス菌には「運動性エロモナス菌」と「非運動性エロモナス菌」の2種類がいます。
運動性エロモナス菌に感染すると、「松かさ病」や「赤斑病」を発症します。
非運動性エロモナス菌に感染すると、体の表面に穴があく「穴あき病」を発症します。
どちらのエロモナス菌も、生体が元気ならば感染の心配はありません。
ですが、免疫力が落ちているなどの感染しやすい条件が揃うと発症します。
腹水病に関係しているのは運動性エロモナス菌であると考えられています。
なぜなら、腹水病を発症したベタに、松かさ病や赤斑病が併発することがあるからです。
次に考えられる原因が、消化器系の内臓疾患です。
餌が合わなかったり、食べすぎたりする事で消化不良を起こし、腹水が溜まってしまう場合があります。
また、ストレスが原因で腹水病を発症することがあります。
腹水病の治療で重要なのは「早期発見・早期治療」です。
食欲が落ち、元気が無く、なんとなくお腹が膨らんでいるなと感じたら、すぐに治療を開始しましょう。
腹水病の治療には「薬浴」を行います。塩浴を併用するとなお効果的です。
使う薬剤は「グリーンFゴールド」や「観パラD」、「エルバージュエース」です。
腹水病は初期症状で治療することが大事なので、「おかしいな?」と感じたら、すぐに治療を開始しましょう。
ベタの水カビ病
水カビ病とはベタの体の表面に綿のような白いモヤモヤができる病気です。
水カビ病が進行するとカビの侵食面積が増えていき、ベタは衰弱死してしまいます。
また、エラが水カビ病に侵されると呼吸困難になって死んでしまいます。
ベタの体表に現れる白いモヤモヤの中でも見た目が綿のような症状ではなく、ベタ全体を薄い膜のようなものが覆うことがあります。
そのような白いモヤモヤはベタの粘膜剥離にておこることがあります。
水カビ病の原因と治療方法
水カビ病の原因は、水中に常在している「真菌」です。
常に水中に存在している真菌ですが、健康な魚には寄生しないので、水カビ病を発症しません。
魚の体表が傷ついていたり、免疫力が落ちている時などに真菌が感染し、水カビ病を発症します。
ショーベタの長いヒレは引っかかりやすく、引っ掛けた傷から水カビ病が発症することがあります。
また、新しい水槽に移動する際に体が網などで擦れ、体表に傷がついたところに真菌が寄生し発症することがあるので注意しましょう。
ベタの水カビ病は自然治癒しにくい
ベタの水カビ病は放置しておいても自然治癒することはほとんどありません。
水カビ病の治療には「塩浴」と「薬浴」が効果的です。
水カビ病でベタが死んでしまう原因は、魚の体内と飼育水との浸透圧の差の調節ができなくなり、衰弱して死んでしまうのが主な原因です。
そのため、外側(飼育水)の環境を0.5%の塩水にすることで、魚の体内との浸透圧差を無くします。
これにより魚の体液の流出が抑えられ、体力の消耗を抑えられるので、薬浴と塩浴を合わせると治療効果が高まるのです。
ベタの水カビ病の治療は隔離容器で行うようにします。
薬浴を行う前にベタの体表に付着した水カビを、ピンセットや綿棒などで取っておきます。その後、治療用の隔離容器に移します。
ベタの水カビ病治療にメチレンブルーが効果的
ベタの水カビ病治療に使う薬剤はメチレンブルー系です。
初期の水カビ病でしたら、塩水とメチレンブルーで治療可能です。
もしくは、アクリノール入りで細菌の二次感染を防ぐ効果が期待できるグリーンFリキッドもおすすめです。
重症化した水カビ病の場合は、グリーンFゴールド顆粒を使います。
水カビ病は他の病気(例えば尾ぐされ病)と併発することがしばしばなので、ベタの状態をよく観察して、他の病気が混在していないか確認してください。
他の病気の症状も見られたら、そちらの病気も治療できる薬剤を使いましょう。
グリーンFゴールド顆粒は幅広い病気に効果があるので、迷ったらこちらを使うと良いでしょう。
腹水病と水カビ病は薬で完治するか?
腹水病と水カビ病は薬を使った薬浴を行えば、完治するのでしょうか。
結論から言えば、「重症化したものは完治が難しい」です。
特に腹水病は、末期症状からの完治が難しい病気です。
腹水病は治すことがとても難しい病気です。
そのため、初期症状での治療開始が重要です。それ以降になると、完治する確率はかなり低くなります。
腹水病の初期症状はどのあたりかというと、食欲が落ちて動きが鈍くなったあたりです。
この段階で治療を始めると完治が見込めます。
ですが問題は、この段階で「腹水病に罹っている!」と、判断しづらいという点です。
また、お腹がパンパンになっていたとしても、「食べ過ぎ」や「便秘」などでもお腹がパンパンに張るので、見分けがつきにくいという難点があります。
そのため腹水病だと気付いた時にはすでに末期になってしまっているというケースが多いのです。
腹水病を見分けるのは難しいですが、次のような場合はなんらかの異常があると考えられます。
- 食欲が無くなった
- あまり動かなくなった
- フレアリングしなくなった
このような状態はなんらかの異常が起こっていると見てよいでしょう。
なので、特にこれ以外の症状が見られなくても、まずは塩浴から治療を開始してみるといいでしょう。
もしそれでも症状が改善されなければ、薬浴を合わせた治療を行います。
お腹がパンパンになったり、糞が白くなるといった状態は、腹水病の末期症状です。
この状態から回復させるのは、正直かなり厳しいですが、それでも諦めず治療は行ってみてください。
ベタの水カビ病も重症化すると治らない
水カビ病の場合も、症状が進むと完治が難しくなります。
水カビの割合が体表の1/3以上まで広がると、かなり厳しい状態です。
そこまで広がる前に治療を開始しましょう。
水カビ病は腹水病と違い、見た目ですぐに分かるので、ベタを毎日観察していたら、見逃すことは少ないと思います。
水カビ病を発見したら、すぐに治療を開始してください。
腹水病・水カビ病ともに、早期発見・早期治療が完治率を高めます。
毎日ベタを観察して、少しでも異変を感じたら、すぐに治療を開始してください。
ベタが罹りやすい病気まとめ
- ベタも他の熱帯魚と同様に尾ぐされ病や腹水病、水カビ病などにかかりやすい
- お腹に水が溜まってパンパンになるのが腹水病。ハッキリとした原因は分かっていない
- 食欲が落ちたらなんらかの病気を疑う
- 腹水病、水カビ病ともに重症化すると完治が難しい。早期の治療が大切
今回はベタが罹りやすい病気についてご紹介しました。皆様のベタ飼育の参考にしていただけると幸いです。