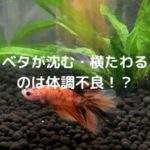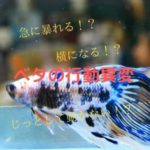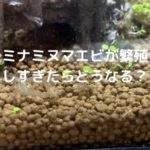ベタの多頭飼いの注意点は?
ベタを複数飼育したい時はどうすればいい?
ベタの水槽を複数用意するメリットとデメリットは?
ベタの水槽を仕切り板で仕切るメリットとデメリットは?
ベタ水槽の仕切りは自作できる?
こんなベタを複数飼いたい時の疑問についてご紹介いたします。
目次
ベタの多頭飼いの注意点は?
闘魚と呼ばれるベタはとても闘争心の強い熱帯魚でよく小競り合いをします。
そんなベタを一つの水槽で多頭飼いすることはできるのでしょうか?
また、多頭飼いする際はどのような事を注意すると良いのでしょうか?
基本的にベタは一つの水槽で1匹ずつ飼育する単独飼育が基本です。
しかし、条件によっては多頭飼いできるケースがあります。その条件とは
- メスのベタを多頭飼いする
- 稚魚の時から同じ水槽で育ったベタ同士での多頭飼い
ベタは縄張りを主張し他の魚を排除しようとする気性の激しい熱帯魚です。
しかし、この習性が強いのは基本的にオスのみです。
ベタのメスはそれほど気性が激しくないので、メス同士であれば多頭飼いする事ができます。
一方ベタのオスは、基本的に1つの水槽で1匹のみ飼育する単独飼育が基本です。
しかし、ある条件下で育ったオスの場合のみ、同じ水槽で多頭飼いする事ができます。
それは、「稚魚の時から同じ水槽で飼育しているオス同士」です。
この場合、稚魚の時から一緒に育ったからか、お互いを敵視しません。
そのため、縄張りを主張して喧嘩することも無いので、大人になっても一緒の水槽で飼育することができます。
ただし、これも絶対ではありません。
成長段階で急に攻撃性を発揮するオスもいます。
また、一度別々の水槽で単独飼育してから、また一つの水槽で一緒に飼育しようとした場合も喧嘩します。
やはり、一度他のオスから離れて自分の縄張りを意識してしまうと、稚魚から一緒に育ったオス同士でも縄張りを主張して喧嘩するようになるのです。
稚魚からずっと一緒に飼育していれば、オス同士であっても多頭飼いできる確率は高まります。
ただし、オス同士の多頭飼いでのデメリットが1つあります。
それは「フレアリングしなくなる」という点です。
多頭飼いできるという事は縄張りを主張しないという事です。
という事は、縄張りを主張して威嚇する「フレアリング」も当然しません。
フレアリングをしないという事は、オスのベタの最大の魅力であるヒレが育たないという事になります。
なので、オスのベタのヒレを、ベタらしく大きく美しく育てたいと言う時には、やはり単独飼育でしっかりフレアリングさせた方が良いです。
以上のように、メスのベタや稚魚から一緒に育ったオスのベタなどは、注意点を守って飼育すれば多頭飼いできます。
しかし、それも絶対では無いので、喧嘩が起こった時に隔離できるよう別水槽を用意しておいた方が安心です。
ベタを複数飼育したい時はどうすればいい?
気性の荒いベタを複数匹飼育したいという場合、どのような方法で飼育すれば良いのでしょうか?
前述の通り、メスのベタであれば一つの水槽で多頭飼いすることも可能です。
ですが、オスのベタの場合、基本的に1つの水槽で1匹を飼育する「単独飼育」が基本となります。
そんなオスのベタを複数匹飼育したいという場合、どのような飼育方法があるのでしょうか?
オスのベタを複数匹飼育する方法は次の2つです。
- 水槽を複数用意して飼育する
- 一つの水槽内に仕切りをつけて飼育する
ベタの数だけ水槽を用意するか、一つの水槽内に仕切りを設けて一つの仕切り内に1匹ずつ飼育するか、このどちらかの方法になります。
ご自宅の飼育スペースや、やってみたい飼育スタイルによって、どちらの飼育方法がより適しているか変わります。
それぞれのメリット・デメリットを順番に見ていきましょう。
ベタの水槽を複数用意するメリットとデメリットは?
オスのベタを複数匹飼育する方法として最も多いのが、ベタ1匹につき水槽を1つ用意するという方法です。
アクアショップで見かけるベタも、このスタイルで飼育されている事がほとんどです。
ベタ水槽を複数用意するという飼育方法のメリットとデメリットを簡単にまとめます。
【メリット】
- 設備がシンプル
- 容器は水槽でなくても良い
- 水質管理がしやすい
- 病気が蔓延する心配が少ない
- フレアリングさせやすい
【デメリット】
- 温度管理が面倒
- 本数が増えると水換えに時間がかかる
- 本数が増えると置き場所に困る
- 水槽レイアウトが楽しめない
水槽を複数用意してベタを飼育する場合、基本的に「ベアタンク」での飼育になります。
ベアタンクとは水槽と水と生体だけというとてもシンプルな飼育スタイルです。
そのため設備がとてもシンプルです。
フィルターや底砂、水草などが不要なので、これらにかかる費用や管理の手間が無いというのが大きなメリットです。
そのため、複数の水槽を用意しても、それほどお金がかかりません。
また、容器は水槽でなくてもOKです。
水量が2リットル以上入るのであれば、お洒落なビンなどでも飼育できます。
そのため、複数の飼育容器を用意するのも難しくありません。
複数水槽での飼育は基本的にベアタンクで行うため、水換えは全ての水を交換する全換水です。
水量や季節で換水頻度は変わりますが、2日~3日に1回か、1週間に1回のペースで水換えします。
水が汚れる前に毎回全換水するので、水質を一定に保ちやすく、水質管理が楽です。
また、たとえ一つの水槽で病気が発生したとしても、それぞれの水槽が分かれているので病気がうつる心配がありません。
複数水槽での飼育はフレアリングさせやすいというのも大きなメリットです。
それぞれの水槽の間には目隠し用の仕切り板を入れるのですが、これをただ外してベタ同士が見える状態にしてあげるだけで、安全にフレアリングさせる事ができます。
この仕切り板は厚手の紙などで十分なので、用意するのも簡単です。
以上のように、水槽を複数用意するメリットを一言で表すと、「シンプルで管理が楽」と言えます。
しかし逆に、このシンプルさがそのままデメリットにもなります。
ベタの複数飼育用の水槽は、小さなサイズの商品が多いです。
入る水量が少ないので、外気の影響ですぐに水温が変化してしまいます。
水温を管理するためにヒーターなどを設置したいのですが、水槽が小さく水槽内にヒーターを設置できないケースが多々あります。
また、ヒーターを設置できたとしても、水槽が複数の場合それぞれの水槽にヒーターを用意するのは費用がかかります。
なので、ベタの複数水槽の水温管理は、飼育部屋の室温をエアコンで丸ごと管理するというのが一般的な方法です。
このように、通常の水槽のようなヒーターを使った温度管理が難しいというデメリットがあります。
また、飼育水槽が増えるほど、水換えの手間と時間が大幅にかかってしまうというデメリットも。
毎回全換水して水槽を洗うので、飼育環境自体は清潔に保てて良いのですが、水槽の数に比例して掃除にかかる時間が長くなります。
水量2リットル程度の水槽を8本ほど掃除して全換水するのに、だいたい1時間くらいはかかってしまいます。
水槽が2本~3本程度の時は楽ですが、水槽が10本以上になるとなかなか辛いです。
これを解消するには、まとめて全部の水槽の水換えをするのではなく、毎日1本~2本ずつローテーションで水換えしていくようにすると良いでしょう。
水槽の数が増えると置き場所に困る事もしばしば。
複数のベタ水槽を並べることを通称「ベタマン(ベタマンションの略)」と言いますが、お気に入りのベタをどんどん購入していると、あっという間にとんでもない数の本数になり、スペースが足りなくなります。
なので、闇雲にベタの数を増やすのではなく、ベタマンの設置スペースを作り、そのスペースに置けるだけの水槽の本数に限定した匹数のベタを購入し、飼育するようにした方が良いです。
最後に、複数飼育は設備がシンプルな方が管理しやすいので、基本的に水草などは入れません。
そのため、水槽を水草などでレイアウトしたい人には少し物足りない水槽になってしまいます。
以上が複数水槽を用意して飼育する方法のメリットとデメリットです。
個人的にベタの飼育方法としておすすめなのが、この複数水槽を用意する飼育スタイルです。
水槽の本数が増えると水換えの手間は確かにかかりますが、水質管理がしやすく病気らしい病気もほとんど発生しないので、ベタを長く健康に飼育するならこの飼育スタイルが良いと感じています。
複数水槽を並べられるスペースがある方は、ぜひこの方法で飼育してみてください。
ベタの水槽を仕切り板で仕切るメリットとデメリットは?
オスのベタを複数匹飼育するもう一つの方法が、「一つの水槽内を仕切り板で区切って飼育する」という方法です。
水槽1つで複数匹飼育するこの方法のメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 水槽一つで3匹~4匹飼育できる
- 複数水槽のようにそれぞれの水槽を管理する手間が無い
- 水槽が立ち上がれば水質管理が楽
- 物理濾過と生物濾過が働くので全換水する必要がない
- 水量が多く水温管理がしやすい
【デメリット】
- 仕切りがあるために水がうまく循環しない事がある
- 病気がうつるリスクがある
- 仕切りに挟まったり、すり抜けるリスクがある
- フレアリングさせずらい
なんと言っても水槽一つで複数匹飼育できるというのが最大のメリットです。
60cmコンパクトタイプの水槽であれば、3匹~4匹のベタを飼育する事ができます。
そのため、複数水槽のようにそれぞれ個別の水槽を一つずつ管理するという手間がありません。
一つの水槽をしっかり管理してあげれば、そこに入っている複数のベタの健康を一度に守る事ができます。
また、一つの水槽を仕切って使う場合、底砂やフィルターなどを設置し、水槽を立ち上げて飼育環境を整えてからベタを導入します。
この水槽を立ち上げる作業は、濾過バクテリアを増やして生物濾過が回る環境を作るという事です。
また、フィルターも設置するので物理濾過も働きます。
そのため、しっかりと水槽を立ち上げれば、水質が安定しやすくなり、水質管理が楽になります。
水質管理が楽だと言える理由の一つが、「全換水しなくて良い」という点です。
ベアタンクの場合は物理濾過はもちろん、生物濾過も期待できない(濾過バクテリアがほとんどいない)ので、全換水することで水質を維持していました。
ですが、物理濾過と生物濾過が働いている水槽なら、フィルターで汚れを物理的に除去し、さらに濾過バクテリアが汚れを分解してくれるので水が汚れづらくなります。
よって全換水ではなく、1~2週間に一度、1/3程度の水を交換するだけで水質が維持できます。
ベタを複数飼育しても水換えの手間がそれほどかからないというのは大きなメリットですね。
また、水槽サイズが大きいので、水量も多く水温の変動が起こりづらいのも良い点です。
水質や水温が維持しやすく、水換えも楽な仕切り板での飼育はメリットばかりに見えますが、一つの水槽を仕切り板で仕切るからこそのデメリットもあります。
仕切り板の多くはメッシュ状になっています。
なぜなら飼育水を堰き止めてしまわないようにです。
ですが、たとえメッシュ状とはいえども、何も仕切りが無い状態に比べると、多少水の流れが遮られ鈍ってしまいます。
これにより水がうまく循環せず滞留してしまう箇所ができ、汚れが溜まってしまう場合があります。
これを解消するために、フィルターの種類や水流の強さ、水の吐き出し口の向き、吐き出し口の形状などを工夫しなければいけません。
ベタに負担が無いように飼育水がうまく循環する水の流れを作らなければいけないのが少々面倒です。
次に、水槽内の1匹のベタが病気に罹った場合、他のベタにまで病気がうつってしまう危険があります。
仕切りがあるとはいえ水槽内の飼育水は共通です。
そのため、感染力が高い病気が発生した場合、水槽内の他のベタにまで病気がうつり、最悪の場合全滅する事もあります。
病気を発症したベタを見つけたら、すぐに隔離して治療し、病気が蔓延するのを防いであげましょう。
仕切りと水槽の間に隙間が空いていると、ベタが隙間に挟まったり、仕切りの外にする抜けてしまう場合があります。
挟まって体に擦り傷がついたり、仕切りをすり抜け他のオスベタと喧嘩してボロボロになってしまうというケースもあるので、極力隙間が無いように仕切りをセットしましょう。
一つの水槽を仕切って使う上での大きなデメリットが「ベタ同士のフレアリングがさせずらい」という点です。
1匹ずつの個別水槽なら、水槽の間の目隠しを取ってあげれば、隣の水槽のベタと勝手にフレアリングしてくれます。
しかし水槽が一つの場合、ベタを区切る仕切り板を取ってしまうと、隣のベタとの間に何も無くなってしまいますよね。
これではフレアリングするだけに収まらず、実際に喧嘩が始まってしまい、どちらかのベタがボロボロに傷ついてしまいます。
「それなら仕切り板を透明にしたら?」
確かにこれなら姿は見えても区切られているので安心です。
しかし、四六時中相手のベタの姿が見えていると、最初はフレアリングしていても、そのうち全くフレアリングしなくなります。
これは、長くフレアリングして疲れてしまうのと、相手が見えている環境に慣れてしまうのが原因です。
なので、仕切り水槽のベタをフレアリングさせる場合には、スマホでベタの動画を再生して見せたり、ペンなどの先の尖ったものを水槽に近づけるなどしてフレアリングさせると良いでしょう。
このように、複数水槽を用意する場合も、一つの水槽を仕切って使う場合も、どちらもメリット・デメリットはあるので、どちらの方がよりご自宅の環境で扱いやすいか考慮して選ぶようにしてください。
ベタ水槽の仕切りは自作できる?
一つの水槽を仕切ってベタを飼育したいという場合、水槽サイズにちょうど合う仕切りがなかなか見つからない事も多々あります。
そのような時は仕切りを自作してみましょう。
ベタ水槽の仕切りは100均にある道具などを使って自作することができます。
最も簡単に安く作れる方法は、100均に売っている園芸用の鉢底ネットとレールファイルのレール、キスゴムを使って作る方法です。
上記を使った仕切りの自作方法は以下の通りです。
- 水槽の奥行きと高さを測る
- 測ったサイズに合わせて鉢底ネットを切る
- 両端をレールで挟む
- 水槽に設置し、仕切りが動かないようにキスゴムで挟むように止める
まずは水槽の内径の奥行きと高さを測ります。
仕切りの高さは水槽の上蓋に干渉しない高さにして下さい。
次に、測ったサイズに鉢底ネット切り、水槽に入るか確認します。
サイズに問題がなければ、両端にレールファイルのレールを取り付けます。レールが長い場合には、鉢底ネットのサイズに合わせて切って下さい。
再度水槽に入るか確認し、問題なければそのまま水槽内に設置します。この時、水槽内に底砂が敷いてあるなら、底砂に仕切り板を差し込むようにして設置しましょう。こうすることでグラつきにくくなります。
また、仕切り板の前後の水槽面にキスゴムをくっつけて、仕切り板を固定しましょう。仕切り板の下部が底砂で固定されているので、上部はキスゴムで挟み込むようにして止めます。
以上が100均の材料で自作するベタの仕切り板の作り方です。
鉢底ネットの強度が足らず、1枚ではペラペラしてしまう時は、2~3枚重ねて強度を上げると良いでしょう。
また、鉢底ネットの代わりに塩化ビニル板を使って作る方法もあります。
こちらの方が強度が上ですが、穴が空いている塩化ビニル板が無い場合には、ドリルなどで穴を開ける必要があります。
また、ベタが傷つかないよう、ヤスリでバリ取りをするなど、加工に少々手間がかかるのが難点です。
今回は仕切り板の簡単な作り方をご紹介しましたが、色々な材料を使った仕切り板の自作方法があります。
- 仕切り板をメッシュ状にする
- 仕切り板と水槽の間になるべく隙間を作らない
以上の2つのポイントを押さえれば、作り方は自由です。
ぜひ、使い勝手の良い仕切り板を自作してみて下さい。
自分で水槽の仕切りを作るのがなんだか難しいと感じる方には販売されている仕切り板がおすすめです。
ベタの多頭飼いの疑問まとめ
- メスのベタは一つの水槽で多頭飼いできる
- メスを多頭飼いするときは3匹以上の匹数を一緒に飼育する
- オスを複数匹飼育する方法は、水槽を複数用意するか、一つの水槽を仕切って飼育する方法の2つ
- 水槽を複数用意する方法は設備がシンプルで管理しやすい
- 仕切り板で区切る方法は水換え頻度が少なくて済む
- 仕切り板は100均のアイテムを使って自作することもできる
今回はベタの多頭飼いに関する疑問についてご紹介しました。皆様のベタ飼育の参考にしていただけると幸いです。
フィルターを設置できない小さな水槽の水をきれいにするベタ・ストーン