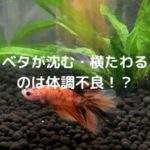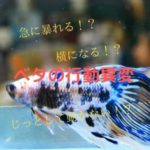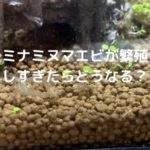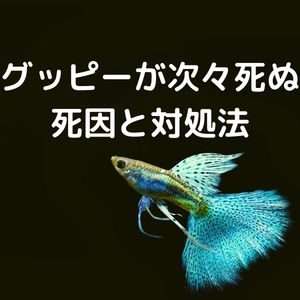
グッピーが次々死ぬのはなぜ?原因は?
グッピーの死因で多いのは?
グッピーが死にそう、死にかけの時はどうすればいい?
グッピーが死んだらどうなる?浮く?沈む?
こんなグッピーの死に関する疑問についてご紹介いたします。
目次
グッピーが次々死ぬのはなぜ?原因は?
せっかく迎え入れたグッピーが次々と死んでいくのを目の当たりにするのはとてもショックな事です。
1回のみならず何度もグッピーを全滅させてしまった経験がある方も多いと思います。
しっかり世話をしているはずなのに何故グッピーが次々と死んでしまうのか?理由がわからない。
今回はそんなグッピーの死や、死にそうなグッピーを回復させる方法についてご紹介いたします。
ですがここで1つお断りをさせていただきたいことがあります。
それは、グッピーが死ぬ本当の原因を特定することは難しく、回復させるための特効薬を断言することもできないということです。
ただ人間でもグッピーでも確実に言えることは、「病気を予防しながら生活すること」、「万が一病気になってしまっても早期に発見すること」、「適切な治療をすること」、このようなことが大切であるということです。
グッピーの飼育にある程度詳しい方は「グッピーはよく増える。しかしその分死にやすい」というイメージも持っていることが多いものです。
この考え方はあながち間違ってはいません。
水槽内の飼育密度が濃くなる程、水槽内の環境は自然界の状態から遠のいていきますし、管理するグッピーの数が増える程手間がかかることになります。
これは個人が自宅でグッピーを飼育している時だけに限りません。
卸されたショップや、その前の入荷の段階においても言えることです。
グッピーは改良に改良を重ねられた種の熱帯魚であり、アクアリウムにおいて大変な人気を誇っています。
そのため、需要が高く大量生産しないと供給が追いつかないのです。
よって、ショップもグッピーの健康状態をしっかりと管理することは容易ではなくなってきています。
もし買ってきたばかりのグッピーが、1匹だけではなく次々と死ぬ場合、必ずしも購入者の飼育方法に原因があるわけではないということが言えます。
グッピーは強くて丈夫な熱帯魚だと言われています。
これも確かにその通りではありますが、グッピーの健康寿命を真剣に考える場合、世間で言われている程強くないと思って飼育するくらいが丁度良いです。
グッピーが「次々と」死ぬ場合の原因の多くは「水質の問題」と「水温の問題」の2つに行き着くと考えられます。
水質と水温を適切に保つことは一見簡単そうに見えますが、実は奥が深く、一筋縄では行かないことが多いものです。
水槽の匂いを嗅いで明らかに怪しい匂いがしていたら水質が悪化していると判断はできますが、必ずしも 「臭くない=水質は問題ない」というわけではありません。
次の章で具体的に水質の問題と水温の問題についてご紹介いたします。
グッピーの死因で多いのは?
前述したようにグッピーの死因は大きく分けて水質の問題と水温の問題にたどり着きますが、そこから細かく掘り下げて考えてみましょう。
そこで挙げられるグッピーの死因は次のようなものになります。
- 水槽内のpHが適切ではない。変化が大きい。
- 水温が適していない。変化が大きい。
- 餌の与えすぎと掃除不足。
- 酸素の不足による酸欠。
- 混泳相手との相性が悪い。
- 水流が強すぎる。
- 餌不足による餓死。
このような問題から病気を引き起こして死んでしまうことも少なくありません。
それでは1つずつ見ていきましょう。
水槽内のpHが適切ではない。変化が大きい。
まずは水質とphが原因の場合です。
グッピーにとって適した水質が保たれているか、定期的にチェックすることが重要です。
水質が悪化するとphは徐々に下がり、グッピーの好むphを大きく外れてしまうこともあります。
もし pHが適正値から外れていると、グッピーはストレスを受けて免疫力が下がります。
グッピーにとって適切な pH値は6.5~7.5位で、弱酸性~弱アルカリ性です。
原種のグッピーはもう少しphの高い水域で生活していますが、日本で販売されているグッピーは養殖されたものが多いため、日本の水質に近いphに慣れています。
また、グッピーには大きくわけて外国産グッピーと国産グッピーがいますが、小さい頃からの水質の影響により外国産グッピーの方が国産グッピーより多少高いphを好むと言われています。
ただ、どちらのグッピーも先に挙げましたph値の範囲で飼育していれば問題ありません。
さらにグッピーの新規導入時や大掛かりな水換えによる急激なphの変化もグッピーの死因に繋がることもあります。
グッピーの購入や水換え後すぐになんだかグッピーがふらふらしている場合にはペーハーショックを受けてしまっている可能性があります。
ペーハーショックは一度そのような症状が出てしまうと治す方法はなく、グッピーの生命力を信じるしかありません。
よってグッピーがphショックを起こさないようにしっかりとした水合わせを行うようにしましょう。
水温が適していない。変化が大きい。
グッピーの適応水温は20~28℃ほどで、適温は26℃前後です。
この水温を大きく外れるような環境はやはりグッピーの体調不良へと繋がり、死因になることもあります。
もちろんph同様に急激な水温変化もまたグッピーに大きな負担をかけることになりますので注意が必要です。
餌の与えすぎと掃除不足
餌の与えすぎや掃除不足もグッピーの死因に影響を与えます。
グッピーが餌を食べる姿は非常にかわいいもので、ついつい餌を与えたくなってしまいますが、餌の与えすぎは色々な問題を引き起こしますので控えなければなりません。
餌を与えすぎることによるグッピーの肥満と消化器官への負担はグッピーの寿命を縮めることにつながります。
ただ、この問題でグッピーが次々死ぬということはないので長い目で見た時の問題です。
餌の与えすぎによって起こるもう一つの問題が水質の悪化です。
餌をたくさん与えれば当然食べ残しが増えますし、グッピーの糞も増えます。
この状態を放置してしまうとあっという間に水質は悪化してしまいます。
餌の量を適正におさえつつ、しっかりとした掃除を行うようにしましょう。
酸素の不足による酸欠
酸素不足もまたグッピーのグッピーが死んでしまう原因の一つです。
過密飼育によって水中の酸素が不足してしまう場合や水温の上昇による水中の酸素量の低下などが原因となることもあります。
ここからは水質や水温の話ではありませんが、グッピーが死んでしまう原因にもなることですので一緒にご紹介いたします。
混泳相手との相性が悪い
まずは混泳させている魚との相性です。
他の魚に常に追いかけ回されるような環境はグッピーのストレスになります。
長くヒラヒラしているグッピーの尾びれは他の魚のターゲットにされやすく、ひれを嚙まれることもあります。
噛まれた所から細菌感染してしまい、病気になってしまうこともあります。
もし水槽にグッピー以外の魚を導入することがあれば、導入後数日間は、その魚との相性をよく観察しましょう。
水流が強すぎる
グッピーは強い水流があまり得意ではありません。
特に稚魚や尾びれの大きいオスは水流に流されやすいものです。
水流に逆らいながら泳ぎ続けることで疲弊してしまい体力を消耗してしまいます。
まったく水流が無い環境もまた水が淀みやすいなどの問題がありますので適度な水流を確保しつつ、グッピーが休める場所などを作ってあげると良いでしょう。
餌不足による餓死
最後に餌不足による餓死についてです。
実は小型のグッピーには胃袋がありません。
よって、口から入ってきた餌は腸の中で消化・吸収されています。
胃袋がない分、体内に餌を長い間貯めておくことができません。
また、腸が短いことにより、中型や大型の熱帯魚と比べると餓死をし易いのです。
1つの水槽内でグッピーをたくさん飼育していて過密である場合や、他の魚と混泳させている場合は、餌がしっかり行き渡っていないと瘦せ細っていき餓死してしまうことがあります。
水槽内の全てのグッピーに餌が行き渡るようにするためには、1ヶ所だけに餌を投入するのではなく、 数ヶ所に散らすようにして投入するのが効果的です。
また日頃からしっかりグッピーを観察して痩せてしまっているグッピーがいないかなどもチェックしておきましょう。
グッピーが死にそう、死にかけの時はどうすればいい?
もしグッピーが今にも死にそうな様子だったら、 何とかして元気にさせたいと思うものです。
少しでも回復の確率を上げるためには正しい知識と対処法が必要です。
まずはグッピーがなぜそのような状態になってしまっているのかしっかり状況を把握することから始まります。
先にご紹介しました原因の中で思い当たる節があるか探してみましょう。
その問題を解決し、その後グッピーの治療にあたるようにしましょう。
いくらグッピーの治療を行っても根本的な原因が解決されなければ、同じことを繰り返すことになってしまいます。
それではグッピーが死にかけになった原因別に対処法をご紹介いたします。
病気によって死にかけている場合
恐らくこの原因によるものが1番多いのではないかと思います。
餌の与えすぎや水質の悪化、水温の低下など様々な要因がグッピーの病気を引き起こします。
一口に病気といっても、様々な種類があるのでそれぞれの病気ごとの対処法を知ることが大切です。
病気の中で最もかかりやすいのは、「白点病」です。
これは、「ウオノカイセンチュウ」という寄生虫が魚に寄生することが原因でかかる病気です。
対策として一番簡単で、かつ一番有効なのは、水温を上げることです。
先程、グッピーに適した水温は26℃程度とお伝えしました。
しかし寄生虫による病気の場合は、完治するまで水温を「28℃~30℃」に設定しましょう。
ウオノカイセンチュウは高温に弱いからです。
次に薬浴や水換えを行いましょう。
白点病の次に多いのがエロモナス病です。
これは水中に常駐するエロモナス菌に感染することで発症します。
発症したら起こる症状は、体の一部が赤くなる赤斑病、鱗が逆立ってしまう松かさ病、体表に穴が空く穴空き病です。
これらエロモナス病に対する適切な処置は薬浴です。
最後に尾ぐされ病です。
エロモナス病と同様、水槽内に常駐する細菌である、カラムナリス菌に感染することで発症する病気です。
よってこちらも薬浴と水換えを繰り返すことが最適で確実な処置です。
ケガや外傷により死にかけている場合
混泳相手にヒレを噛まれたり、水槽内のレイアウトに擦ってしまったりしてグッピーがケガをすることがあります。
そのケガを放置してしまうとそこから細菌感染が起こり、病気になってしまうこともあります。
グッピーの怪我の対処ステップは全部で3ステップです。
まず他の魚と隔離します。
次に塩水浴や薬浴を行いましょう。
最後に、すぐに元の水槽には戻さず、回復してからも数日間は「回復期」を設け、しばらくは隔離して飼育しましょう。
酸素不足で死にかけている場合
いわゆる酸欠です。
グッピーは繁殖が容易で増えやすい分、過密飼育によるリスクも高まります。
グッピーを過密飼育すればそれだけ必要な酸素も増えますが、酸素の供給が不足していると酸欠を起こします。
夏の水温上昇による高水温も酸欠を引き起こしやすいので注意が必要です。
急な停電や水中ポンプ・外部フィルターの故障、水温の上昇など、水槽内のグッピーは意外と頻繁に酸欠のリスクにさらされています。
水面近くで口をパクパクさせていたり、普段よりもふらふらしてゆっくりとした泳ぎになっていたら酸欠のサインである可能性が高いです。
まずはエアレーションを行い、水中の酸素量を増やしてあげましょう。
水換えにより新鮮な水を取り込むことも効果的です。
ただ大量の水換えは急激な水温変化や水質変化を招きますので慎重に行うようにしましょう。
過密飼育の場合には新しい水槽を用意して飼育数を減らすなどの対策も必要となってきます。
グッピーが死んだらどうなる?浮く?沈む?
「魚は死ぬと水に浮く」と思っている人は多いかもしれません。
実は魚は死んだ直後は浮かんでこず、また、死んでしまった原因によっては沈むこともあります。
水に浮くことは、体の腐敗と関係しています。
グッピーに限らず、どんな種類の魚でも、普段は浮袋を調節することにより水中で生活をしています。
ですが魚が死んでしまうとその浮袋の機能は停止します。
死後、内臓が腐敗したことにより発生したガスの方が、浮き袋の機能よりも優位になるため、その結果水に浮くことになります。
よって水に浮いているグッピーは死んでからある程度の時間が経っている場合が多いのです。
浮かばずに沈んでいる場合は体内の腐敗が比較的緩やかで、すぐにガスが溜まりにくくなっている状態の場合です。
例えば、もし死んでしまった原因が「餓死」である場合は、体内に餌がほとんど無いということなので、その分腐敗するスピードが緩やかである為、死後2、3日経過していても浮かんでこないことが多いです。
寿命で死んでしまった場合も、食が細くなっている場合が多い為、餓死と同様に沈む傾向にあります。
いずれにせよ、死んでいる魚を見つけたら、水槽内の他の魚が食べてしまったり病原菌が発生したりするのを防ぐために、すぐに掬い出しましょう。
グッピーの死因まとめ
- グッピーが「次々と」死ぬ場合の原因は、水質と水温が関係していることが多い
- 水質の急変や水温の急変もグッピーの死因になることがある
- 餌の与えすぎは水質の悪化とグッピーの病気をまねく
- 過密飼育や水温の上昇はグッピーの酸欠を起こすことがある
- 死にそうなグッピーを見つけたら、回復させる可能性がある処置を落ち着いて適切に施すことが大切
- グッピーは死んでも必ず浮くとは限らない
今回はグッピーの死に関する疑問についてご紹介しました。皆様のグッピー飼育の参考にしていただけると幸いです。